目を閉じて断片的な時間を手繰り寄せ、瞼の裏で像を結ぶ。唇でそれらを形象し肺から押し出された空気が音を与える。発語された記憶は束の間漂い君の耳を震わせる。
地面が雨に濡れる夜。
君と彼女は長い間、テキストのやりとりをしていた。
その夜、2人は初めて対面した。
君が誘ったのか、彼女が家に招いたのか正確に思い出すことは不可能だが、時機が合った。互いの好奇心がその夜の出会いを実現させた。互いに軽い挨拶を交わして近くのスーパーマーケットで夕食を買う。
彼女は君を部屋まで案内すると、テーブルの蝋燭に火を灯す。これまで出会ったことのなかった他者同士が食事をするために同じテーブルにつく。
部屋の窓から見える光はオレンジだったか白だったか。そういったことで自身の記憶の信憑性を測ることはできない。今書いているあの夜についての文章が、フィクションなのか、それとも事実に即したレポートであるのか、君は未だ言い切れないでいる。
君はその夜のほとんどを彼女の話しを聞いて過ごした。
今でも彼女の声を辿ることでその姿、雰囲気を細部まで再び思い描くことができる。
彼女は君に彼女自身の境遇を話した。
昔のボーイフレンドはバンドをしていた。彼は小さな借金をいくつか抱えていて、いつしか彼の歩みは随分と重くなっていた。彼女は献身的に彼を支えていたがいつしか彼は孤独な言葉を発するようになった。それは理解し難く救う手すらも拒むもので彼女は困惑した。それでも彼女は彼の背中に手を当て彼の生を肯定し続けた。そして突然(少なくとも彼女の話しでは君にはそう思えた)彼は死んだ。彼が亡くなり今は彼女が返済しており最低でも3年は続く額が残っていること。過去の記憶とはどうしてこうも物哀しいものばかりなのだろうかと君は思う。唯一、君を救ってくれた話は、彼女には夢があり帽子屋で修行をしていることだった。彼女は人生を共に歩めるパートナーを探していた。君は(そもそもそこへ来たのは間違いだったのだろうか?)相槌を打ちながら歯切れの悪い返事をしていた。
現在へと話しが辿りついたところで、君たちはティーブレイクにした。
彼女は幾つかのハーブが調合された薬草茶を淹れてくれた。
そして彼女は携帯電話のスピーカーで音楽を流し始めた。囁くような女性の声とピアノで構成された美しく調和の取れた音楽だ。そして空のグラスに携帯電話を入れる。音楽を部屋に反響させる音響装置が即席で作られる。
時間は午後11時を過ぎている。
君は椅子を離れて床に腰を下ろす。
彼女は消えかかった蝋燭を新しいものに取り替える。
蝋燭の火が消えて束の間、部屋は暗くなり互いの姿はぼやける。どちらの口からも言葉はない。
マッチを擦る音と香ばしい木が燃える匂いが君に届く。
君は肩を叩かれて目を覚ます。意識はあるはずだったが、いつ椅子に戻ったのかは覚えていない。
帰る時間が過ぎていることを彼女は告げ、君は少し急いで席を立つ。その時にテーブルの角で膝を打つ。互いに言葉は無い。
突如として互いに気を遣う初対面の時間は終わりを迎えていた。君は彼女に目を合わせようとするが彼女は君の手に荷物を押し込むと玄関まで送ると言う。
帰路に就く。既に雨はあがり深夜の道路に人影はない。
午前2時。

生年月日:1995年7月25日
住所:京都府上京区泰童片原町652−4
職業形態:パートタイム
不定期の活動:ダンス分野を中心とする舞台活動
配偶者:なし
身長:175cm
体重:60kg
血液型:AB
処方されている薬:ドグマチール、抑肝散加陳皮半夏、レキソタン、デュタステリド、ミノキシジル
不足項目:亜鉛、EPA、DHA



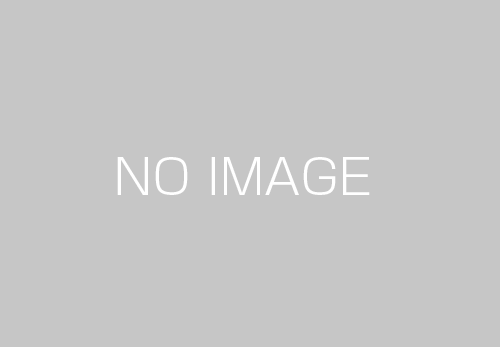


この記事へのコメントはありません。